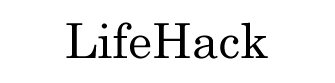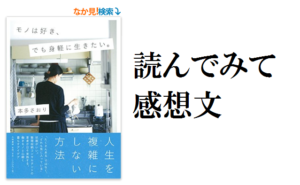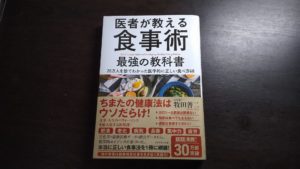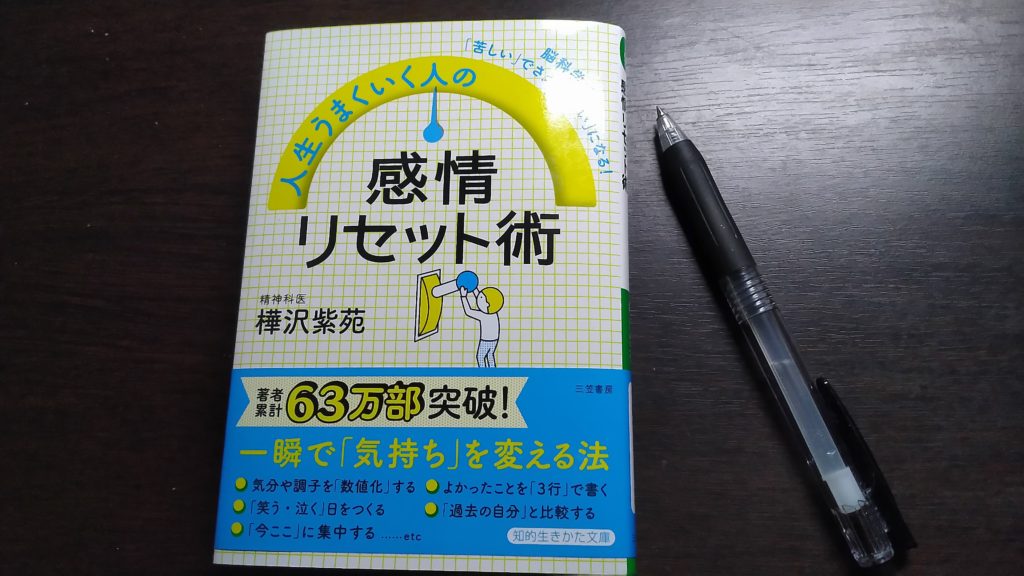
※ 本ページはプロモーションが含まれています。
悩みの迷路に落ちない術
人の生活には沢山の選択肢があって、ある選択肢を選んだら袋小路に入っていく時があります。悩みの沼で抜け出せなくなり、不幸になってしまう。
そんなことにならないように、前もって感情リセット術を読んでおけば、間違った選択をせずに済みます。樺沢先生も、そのために書いてくれている。
昔から、間違った考え方が世の中の当たり前になっているケースが沢山あることに気付きます。医学の知識を少し教えてもらっただけで、そういう間違いを簡単に直せることは、素晴らしいです。
科学的根拠
近年、「エビデンス」という言葉をよく聞きますので、なんなのか観察していました。結局、医学論文で確定した証拠があれば良いわけだ。
生物における確定的な証拠って、難しいですね。
何年も実験を続け、統計をとって分かることのようです。
ストレスで死んでしまうラットと、生き延びるラットの違い。
ん~、自分がネズミだったら、なんとか生き延びたい。
そういう意味で、人間の生活というのは、実験が続いているのです。そして、進化を続けていく。先人に、感謝しましょう。
ポジティブ思考の力
厳しい環境で生活をしていても、一日にプラス効果は沢山出している。
しかし、マイナスの出来事が多いと、頭の中が「マイナスだ~」で満たされて、プラス効果を確認することすら忘れてしまう。
生活環境全体を牽引していくのは、プラス要素だ。この要素を、しっかり確認して称えることで、またやる気が湧いてくる。たとえ、全体がマイナスの結果だとしても、部分のプラスを褒め称えることでしか、プラスの方向に転じていかない。
よって、いかなる環境になっても、プラス効果を探す側に自分を置くことが不可欠だ。中身がピジティブであれば、発展のの可能性はある。
正しい生き方とは健康的な生き方
「正しい生き方」とは何ですか?
人によって正しい生き方は異なるだろう、と言いたいですが、樺沢先生のアドバイスからは、
「正しい生き方=健康的な生き方、体に良い生き方」
そういうことを教えられる。
人類の歴史では、正しい生き方と言い、体に悪い生き方を強制されてことが無数にあるだろう。正しい生き方をうたって人を不幸にしてきた歴史だ。
そういう人間無視の考え方にも警鐘を鳴らしているとも、私には読めます。
機械社会の中の人間
近年の機械社会の進展で、人は不健康にさせられることが増えている。長い労働時間、運動不足。
これらは、機械に人が合わせているから起こる。機械に使われる人間。人の健康が第一にはされていない。
そういう環境で、人間には大きなストレスがかかることが増えているんだ。人間関係のストレスもあるが、機械生活のストレスも増えてきている。
ゆえに、環境を人間中心で、仕事のしやすい、生産効率の上がるものに整える必要がある。そのためには、健康についての知識を学習しておくことは大切だ。
樺沢先生の「感情リセット術」は、そういう問題に対して良いアドバイスをくれている。
私が感情リセットになる時とは

場所を移動したとき
風呂上がり
泣いた後
笑った後
本を読んだ後
朝起きた時
仮眠した時
ノートに書き出した後
パソコンを再起動した時
料理を食べた後
リセットした時は、脳内メモリーが少なくなった時です。 軽くなるので、とても快適になります。現代は、それだけ普段からデジタル情報の処理で脳内メモリーをフルに使っているということです。
小さなプラスを見つけ出す
2年ほど前から 樺沢先生の著書にはまっていますが、きっかけは先生の YouTube 動画であります。
気持ちの整理の仕方とか、ストレスの取り除き方というのには、若い時からとても関心がありまして、 悩んで克服してきたという経緯があります。
それを今改めて科学的に先生が説明してくれていますので、確認しながら読んでいるところであります。
具体的に方法が書かれていますが、特に私も実行しているのが、自分の感情をノートに書き出すということであります。
思っているだけだとストレスになりますが、書き出して目で見ることによって、客観的に自分を遠くから「メタ認知」できるというわけです。 それだけでストレスは軽減されます。
また、近年は情報が過剰に流れていますので、一日にあったプラスのことということをすぐに忘れてしまう傾向があります。 一日の最後に、敢えて自分が見逃していた小さなプラスのことを見直して書き出すということが、自分のモチベーションを上げるということになります。
マイナスが多数を占める時であっても、プラスのことを書き出してそちらに目を向けていくことで、困難を乗り越えていくことができます。
最近の結論としては、脳内メモリーを70%以上にしないで、常に50%未満で保っておくということが、毎日の生活パフォーマンスを上げるコツだと思います。
つまり、一つの事に頑張りすぎると逆効果になるということです。